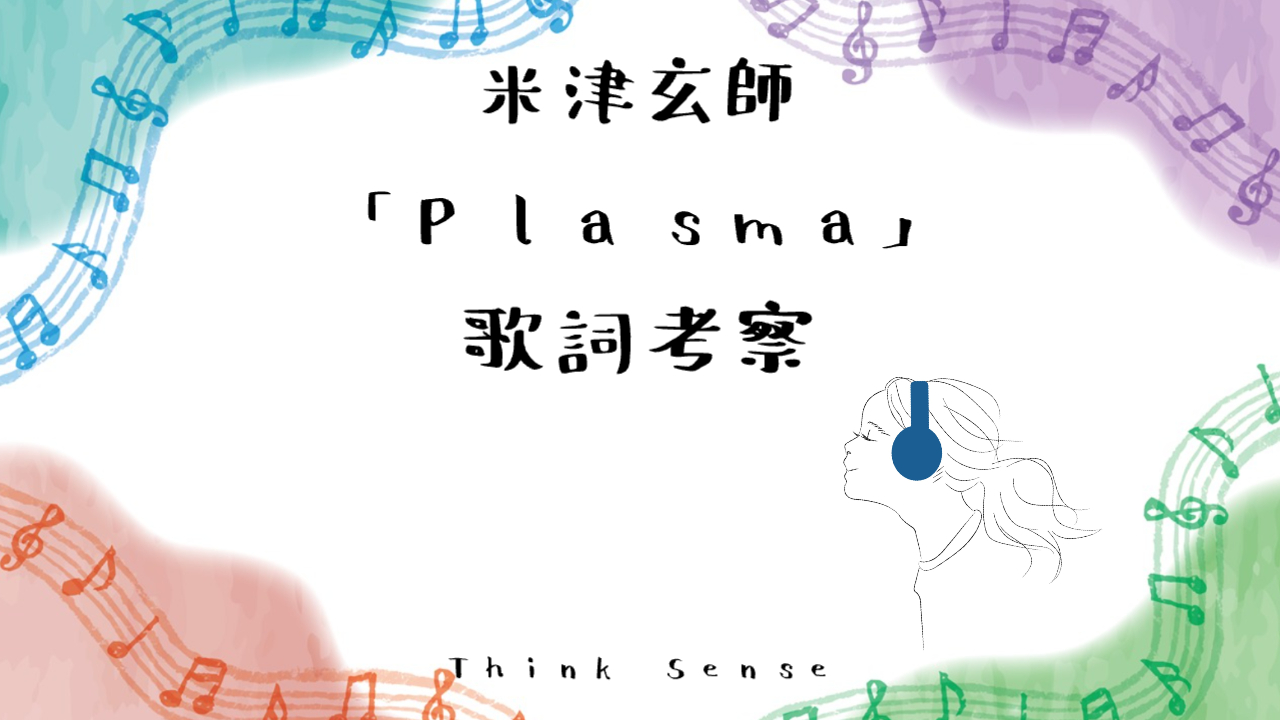こんにちは
今回は、2025年1月20日に配信限定シングルとしてリリースされた米津玄師の『Plazma』についての歌詞考察をしていきたいと思います。
1.[米津玄師]『Plazma』について
米津さんは新曲について「zip」のインタビューを受けた際にこんな事を語っています。
『Plazma』の歌詞を読み取りやすくするためにも、読んでおくといいかもしれません!
“1番最初に音楽を作り始めた頃の喜びみたいなものを再現してみたくて、今までは共同でアレンジとかをしていたのを、まるごと全部自分で済ませたらどうなるかというのをやってみました。
それは子どもの頃実際にやっていた事なので、ある種の自分の無邪気さというものが宿った曲になったと思います。”
“サビの歌詞を書いている時に
すんなりプラズマという言葉がハマって。
高校生くらいの頃、
若い子供たちの狭い世界っていうのがあって、
狭い視野から大きなそれこそ宇宙だったり…
そういうところに向かっていくダイナミズムというか、それを繋げるプラズマっていう表現で作りました。”
つまり、この『Plazma』では若い子どもが狭い世界から広い世界へ踏み出していく時の揺らぎや思い切りというものを描いたことが推測できますね。
それに加えて、米津さんが楽曲制作を始めた頃の喜びを再現するために1人で1から100までを作ったと言っています。
米津さんにとっても原点回帰というか、原点を基盤に置いて作った楽曲だということがわかりますね。
2.[米津玄師]『Plazma』の歌詞
3.[米津玄師]『Plazma』の歌詞考察/解釈
この『Plazma』という曲を解釈するにあたって、1番最初に紹介した「zip」でのインタビューの内容は大変参考になります。
そのインタビューの内容から今回の解釈で留意しておきたいのは…
・米津さんが楽曲制作を始めた頃の喜びを再現しようとした楽曲であること
・若い子どもたちが狭い世界から広い世界へ踏み出していくダイナミズムを描いた楽曲であること
この2つです。
これらを意識した上で歌詞考察/解釈の方、やっていきたいと思います!
3-1. 自らの選択に対する後悔と受容
冒頭の歌詞を丸ごとドーンと移してきました。
この部分、どちらも「もしも〜しなければ、〜だった」という過去に対する回想であることがわかりますね。
米津さんが楽曲制作を始めた頃の初心に立って作曲したことを踏まえると
「あの改札の前で立ち止まった」=「みんなと朝の満員電車に乗ることを選ばなかったこと」
「あの裏門(表ではない門)を越えて外へ抜け出した」=「みんなとは違う道を進んだこと」
を指していると言えます。
つまり、同じく「米津さんがアーティストの道を選んだこと」を指しているということです。
これを当てはめてもう一度解釈すると、
「アーティストの道を選ばなければ、君を知らずに幸せに生きれたのに」という「過去への後悔」
「アーティストの道を選ばなければ、自分が見てきたものは輝くことなく、靴の汚れのようになっていた」という「過去の受容」
この2つを同時に描いていることがわかります。
他の人と違う道を歩むという選択は、悪い面も目立つけど良い面ももちろんあったし、どっちとも言えるということですね。
3-2.行き着いた先もまた行き止まり
※リノリウム: 床板の上に貼る貼る床仕上材のこと。
「逆立ちして擦りむいた両手」とは、普通の生き方とは対に位置するのアーティストとしての生き方をしてきた末に、手が擦り切れるほどの楽曲を制作してきた様子を表しているととれます。
しかし、次には
「ここも銀河の果てだと知って寝転び、目眩がしている」状態であることがわかります。
この部分は、アーティストとして活動し続けることの迷いのようなものが表れているのではないかと考えます。
勿論、私には理屈でしか理解できない話であることを前提として、詳しく解釈してみます。
アーティストとして活動を始めた時、きっと真に自分の内側を表現した曲だけを作ると思います。
しかし、売れるということは多くの人から様々な評価をされるということ。
当然、その中には自分とは異なる解釈をして絶賛する人もいるでしょうし、その異なったイメージで次の楽曲を期待されたりもするでしょう。
そうなってくると、自分の中でやっていきたいアートというのが分からなくなることがある、という話はまあよく聞く話です。
そこで行き詰まってしまうことを「銀河の果て」と表したのではないでしょうか?(邪推だったら米津さんにも読者さんにも本当に申し訳ない…!)
つまり、一般の道とは異なるアーティストとしての道を突き進んだ先もまた「迷い」や「苦悩」に苛まれる行き止まりだったということかもしれません。
この一節、少なくからず私はそう解釈しました!
3-3.「光」が意味するもの
この部分は、まさに「光」に向かって突き進む米津玄師さん自身の姿勢や感情が描かれているように思います。
「聞こえて」「答えて」というフレーズからは、誰かとの繋がりを求める切実な願いが感じられます。
これはアーティストとして、自分の内面を表現する一方で、リスナーとの共鳴や交流を強く求める米津さんの姿勢を表しているのかもしれません。
また、「光って叫んだ」という一節には、自らの存在を必死に伝えようとするエネルギーが感じられます。
この「光」とは、単なる希望だけでなく、米津さんの創作活動そのもの、つまり彼が届けたい音楽やメッセージを象徴しているのではないでしょうか。
さらに、「金網を越えて転がり落ちた」という表現からは、未知の世界に飛び込む覚悟や、その過程での痛みや失敗が読み取れます。
しかし、その「刹那」に「世界が色づいてく」というフレーズが続くことで、挑戦の先には新たな感動や発見があることを示唆しているように感じます。
この部分を通して、米津さんは「どんな迷いや苦悩があろうと、前に進むしかない」という決意を歌っているのではないでしょうか。
そして、その道の先には、きっとリスナーとの深い繋がりや新しい景色が待っているのだと信じているように思えます。
3-4. プラズマ=「今」を生きる爆発的な力
最後にサビの考察です。
この曲の全サビで、米津さんが「プラズマ」を何か巨大なエネルギーやダイナミズムの象徴として使っていることが感じられます。
「ぶち抜く」ってやばいですもんね笑
ダイナミズム全開です!
インタビューでも触れられていたように、プラズマは、狭い世界から広大な宇宙に飛び出していく原動力を表しています。
ここでは、「過去」の痛みや迷いさえも超越し、ただ「今ここ」に存在する自分のエネルギーを感じ取っているような描写が目立っていますね。
また、「痣も傷も知らずに」「踏み出した体が止まらない」という一節からは、目の前の大きな夢や希望に心を奪われ、痛みすら感じないほどの純粋な情熱が伝わってきます。
これこそが、米津さんが「子どもの頃の無邪気さ」と語っていたものに通じるのではないでしょうか。
プラズマは、破壊的な力を持つ一方で、新しい何かを生み出す力も秘めています。
この曲全体を通して、米津さんはその二面性を描きつつ、「どんな困難や変化も超えていく力」をリスナーに伝えようとしているように感じられます。